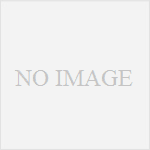あらゆる生物の死亡率は100%、誰も死から逃れることはできません。だから、多くの人が、死生観を語ってきたのでしょう。
千島博士もその1人です。博士は「死」をどのように捉えていたのでしょうか。まず、博士は、生と死は、楯の両面であり、「生」なくしては「死」はなく、「死」なくしては「生」もないとしています。
「死は、生のきっかけ=契機である」という哲学的な考え方をされ、「細胞の死によって、バクテリアが新しく生まれること(新生)」をカエルの観察で確認されました。
千島博士は、昭和29(1954)年、カエルの赤血球が腐敗していく過程をずっと観察し、赤血球から、バクテリアの桿菌が発生する事実を顕微鏡で捉えました。そこで、「死」は「生」のきっかけであることを実証されたのです。
そして、人間も高等動物も、腸内細菌と共生しなければ生きていけないことを、とくに、腸内乳酸菌のおかげで、お互いに生かされて生きているとしたのです。そこにあるのは、弱肉強食ではなく、共存共栄の思想であり、それは人生観にも通じるものとしました。
「自然や生命は、生と死を連続的に繰り返して、螺旋的な反復を通じて、生物は進化している」と説かれました。
これは、東洋、仏教思想の「輪廻」と通じるものであり、あらゆる生物に共通するものです。その第一は、樹木です。地球から人類がいなくなっても樹木は生きられますが、樹木がなくなれば、人間は生きられません。
しかし、多くのところでご神木とされている杉は、一方では、増加し続ける花粉症の元凶にもされています。杉の学名「クリプトメリア・ジャポニカ」には、日本の財産という意味が隠されていることを忘れてはいけません。
たしかに、第二次大戦後、国の方針で盛んに植林されてきた杉やひのきは、緑豊かな国のシンボル的な存在でした。しかし、手入れが行き届かず、間伐もされていない「放置人工林」ばかりになっています。
太陽の光もほとんど入らず、もやしのようなひょろひょろの木や倒れてしまったものもあります。
落葉樹ならば、腐葉土が作られますが、杉の葉は腐らないので、降り注ぐ雨も流れ、下草も生えず、石が露出し、生命力の消えた世界が広がっています。
そうすると、人類などの動物を活かす最大要素の水に影響が出てきます。水質が落ち、界面活性剤の流入がそれに拍車をかけ、川や海の水質汚染は広がるばかり、珪素や鉄分の不足をきたして、生態系全体のバランスが崩れてきます。
ただ、幸いなことに、日本の山林業の救世主というべき人も誕生しています。その1人が、『樹と人に無駄な年輪はなかった』(三五館)の著者・伊藤好則氏です。
伊藤氏は、乾燥させるのが難しく、外国材に押され気味になっている日本の杉の現状を憂い、研究に研究を重ねて、45度を標準温度とした低温木材乾燥装置を開発しました。熱源は電気を使い、全部木でできています。
そして、「変色なし」「薬効を失わない」「酵素を損なわない」「色」「艶」「香り」の3拍子がそろった「香素杉」を誕生させたのです。
伊藤氏は、「これは奇跡だ!」と評される木材乾燥装置を「愛工房」と名づけ、この生まれ変わった杉材を広めるために、「アイ・ケイ・ケイ」と名づけた会社を設立しています。
『祈りの力』
3章 P.90より